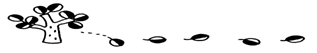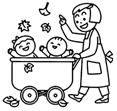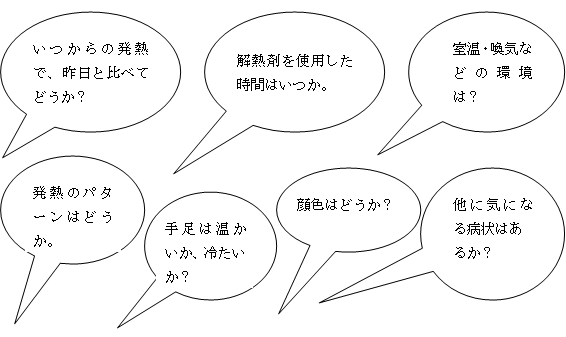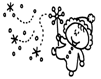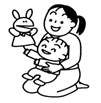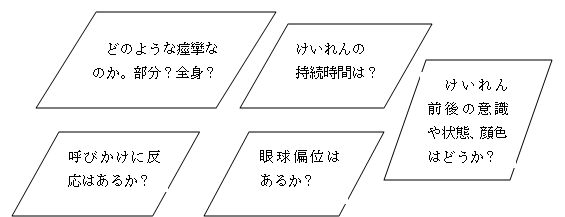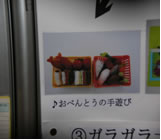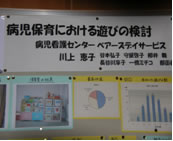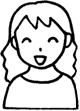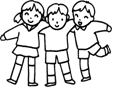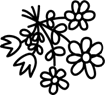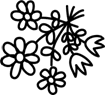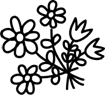病児保育室だより 第9号
松尾小児科内 病児保育室さくら
|
|
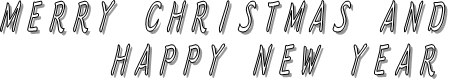
今年も子供たちと一緒に楽しい作品を作りました。来年も“さくら”での一日が楽しいものになるように頑張っていきたいと思っています。 |
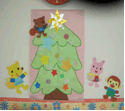 |
病児保育室“さくら”スタッフ |
|
|
 |
 |
小児科より
“さくら”を利用のみなさまへ |
 |
| 昨年の12月にはインフルエンザの全くありませんでしたが、今年は全国で流行しています。さらに、嘔吐下痢症も多くの子どもたちにおそいかかっています。どちらの病気も高熱や嘔吐で水分を取れなくなってしまいます。水分補給が大切な病気です。水分補給にはスポーツドリンクではなく、乳幼児イオン飲料(アクアライト、OS−1など)を使用してください。 |
 |
また、発熱には涼しくしてあげることです。熱の上がり始めには、体がぶるぶる震え手足が氷のように冷たくなることがあります。この状態では手足を暖かくしてあげてください。しかし、手も足も熱くなったら、涼しくしてあげてください。特に、熱があるのにコタツの中で寝かせたり、湯たんぽを使ったりはしないで下さい。熱がこもってしまいます。
今年は、小さな子どもには厳しい冬かもしれません。お母さん、お父さん頑張ってください。 |
|
|
|
| |
 |
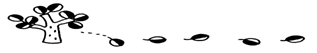 |
第17回全国病児保育研究大会
IN福岡2007
7/14(日)、7/15(月)の2日間にわたり、「拓こう病児保育の未来をー保育士の向上をめざしてー」をテーマにたくさんの先生方からすばらしい話を聞くことができました。
今後求められている質の高い病児保育の実施に向けて病児・病後児保育に携わっている私たちにとって充実した「研修の場」になりました。 |
 |
<保育士 Y・N> |
・・・・・プログラムをご紹介します。・・・・・ |
*基調講演
「多様化する病児保育の資質向上にむけて」
帆足英一先生(ほあし子どものこころクリニック)
*特別講演
「子供の育ちとこれからの子育て支援」
横山正幸(福岡教育大学名誉教授)
*基礎研修プログラム
「看護I」 「保育看護」 「保育I」 「総論」
*教育講演
「保育における病児の印象診断」
武谷茂(たけや小児科医院)
|
*分科会
「病児保育のニーズと問題点」
「病児保育の実践と工夫」
「地域の取り組み」
*ポスターセッション
「保育看護と地域の連携」
「遊びとおもちゃの工夫」 |
⇒「ニーズと問題点」に参加しました。その発表の中に病児保育の存在意義として、単に子供を預かるだけでなく病児保育でなければ実践できない保育看護を社会に還元していくことにあるのではないかとありました。 |
|

(保育看護の講演) |
- 基礎研修では看護師は保育の知識を、保育士は看護の知識を学びお互いの立場を理解しあいます。
|
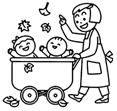 |
|
病気のお子さんをお預かりする時、私たち保育士は保育の知識だけでなく看護や病気への対処法の知識も必要となります。その一部をご紹介します。ご家庭でも参考にしてください。 〜病児保育室“ことりの森”(青森県)の発表から〜
| ◎保育における病児の印象診断 |
| |
初期印象診断・・・ |
子供と合わせて気分や体調など、健康状態の良否を判断し適切に対処することである。
顔つき・顔色・泣き方・咳の音・活気・機嫌・声の調子など |
| ◎病気観察の視点と対処法 |
| |
○発熱・・・ |
一定の測定方法、測定部位、環境条件で体温測定した結果、本人の平熱より1℃以上を発熱としている。一般的に小児では37.5℃以上を発熱としている。 |
| (観察の視点) |
 |
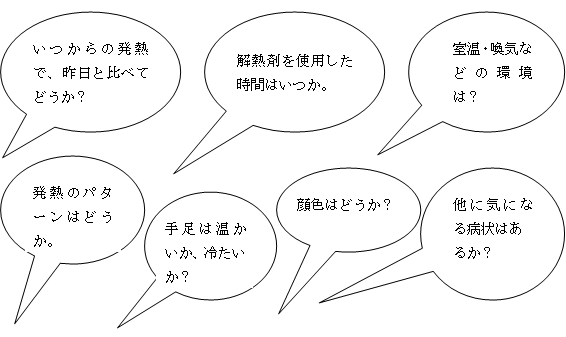 |
(対処法)
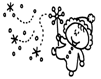 |
・環境の調節をする。
・適切な室温や湿度にする。
・衣服の調節をする。
・水分の補給をする。(適度な水分でも大丈夫。)
・安心・安全の保障。 |
 |
| (ポイント) |
・熱の高さに翻弄されない!!
・手足が冷たい→熱が上がりきっていないので、保温。
・
手足が暖かい→熱の放散のため、衣服を薄くして、ぬるめのタオルで汗を拭き、冷却シートなど。 |
|
| |
| |
○熱性痙攣・・・ |
急に熱があがる時に起こす痙攣。突然意識を失い、目は一点を見つめ、手足はピクピク、又は全身硬くなりガクガクする状態。 |
| (観察の視点) |
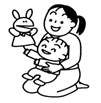 |
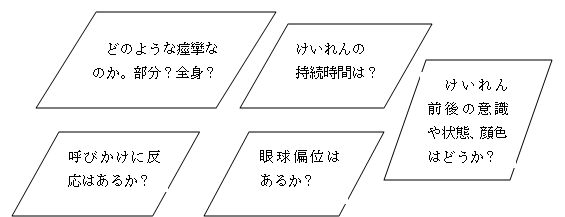 |
(対処)
|
・衣服をゆるめる。
・嘔吐した物がのどに詰まらないように顔や体を横向きにする。
・口に物を挟まない。
・揺すらない。
|
 |
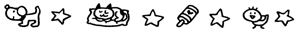 |
| (ポイント) |
・多くは5分以内におさまるので、慌てず落ち着いて対処する。 |
| |
| |
○嘔吐と下痢 |
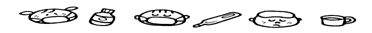 |
(観察の視点)
|
|
|
下痢に血便が混じってないか?(細菌性胃腸炎を疑う。) |
6回以上大量の水様の下痢便が続かないか?(下痢による重度の脱水を疑う。) |
嘔吐mに黄色の胆汁が混じっていないか。経口補水療法でも嘔吐を繰り返さないか?(虫垂炎や腸閉塞などで腸の通過障害があるときがある。) |
腹痛を30分〜60分ごとに繰り返さないか?(腸重積の可能性を疑う。) |
顔色、皮膚の色が改善しない。(抹消循環が悪い。) |
皮膚や唇の感想、排尿がない、あるいは、大変少ない(脱水の進行)などに注意する。 |
|
☆経口補水療法・・・・脱水改善に有効なイオン飲料(0−S1・アクアライトなど)を吐気に注意しながら、脱水改善の目安となる排尿を促す。
(感想)今回の教習では、看護師、保育士、それぞれの専門性を高めるのはもちろんのこと、保育士は保育だけでなく、病気を見極める力、正しい対処の方法などを学ぶことができました。また、地域や保育園などに「保育看護」情報を提供していくことにも病児保育室の役割があると感じました。医師、看護師、保育士の連携を大切に、これからの病児保育室“さくら”を、今まで以上に安心と信頼をもって利用して頂けるようしていきたいと思っています。
|
| ポスター展示では・・ |
 |
各都道府県の病児保育施設がさまざまな取り組みを発表されていました。その中で神奈川県「エンゼル多摩」の保育士、看護師さんの発表をご紹介します。 |
|
よりよい保育看護の実践をめざして |
エンゼル多摩の12年の歩み 保育士・看護師・チームとしての思い |
病状の重い子は護師に見てほしい。 |
この発疹はなに? |
脱水予防が大事!嫌がっても少しずつ飲ませてほしい。 |
1年目
保育と看護が分離していた時期  |
泣き止まない子に何をしてあげたらいいの? |
おたふくって何にきをつけなきゃいけないの? |
下痢の時便の症状は見せてほしい。 |
こんなに熱があるのに預かっていいの? |
何をして遊ばせたらいいの? |
| 看護師の言っていることがわからない。 |
熱がでているのは病気だから対処療法をしよう。 |
下痢の時には脱水に気をつけえて!って言われても飲んでくれない時どうするの? |
伝えたいことが保育士に伝わっている。 |
子供に起こりやすい症状や感染症について勉強会を開いてほしい。 |
2〜3年目
保育と看護が重なり始めた時期

|
子供が安心できるような関わり方や、どんな遊びが好きか、もっと知りたい。 |
症状に気がついてもそれがどういう事か判断に迷う。 |
日頃よく見る疾患についてスタッフ間で勉強していかなくたはならないと思う。 |
発達状況に合わせたケアができるようになってきた |
3年〜
保育と看護の重なりが深まった時期

|
子供の思いをそのまま受け入れ、こどもとの一日を楽しいものに計画していかれるようになってきた。 |
病状にあったケアが出来るようになってきた。 |
子供の病状把握をし、チームとして看ていかれるようになってきた。 |
|
| 「エンゼル多摩」さんの12年の歩みを紹介しました。「さくら」も6年目を迎え、より工夫をしながら、発展していけるように努力していきたいと考えています。 |
(ポスター展示より) |
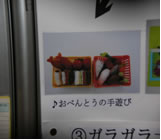  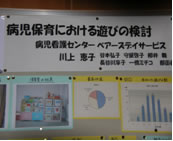 |
各病児保育室でのいろいろな“遊びとおもちゃの工夫”が発表されました。 |
|
|
|
| ▲ ページTOPへ |
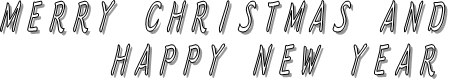
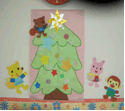

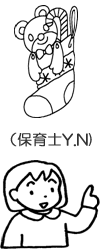



 年末年始のお知らせ
年末年始のお知らせ