病児保育室だより 第6号 松尾小児科内 病児保育室さくら |
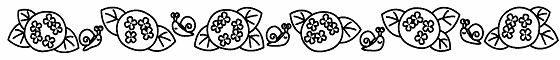
スタッフも一新し、気持ちも新たに子どもたちの健康と安全に努力していきたいと思っています。
 細川 久枝(看護師) |
|
 渡邊 昌代(看護師) |
|
 宮尾 有可里(保育士) |
|
 国里 千春(保育士) |
|
 木村 裕子(保育士) |
|
遊びの計画
| 4月 | ・春の歌を歌う ・絵本を見たり、折り紙を折る |
10月 | ・どんぐりやまつぼっくろを使って遊ぶ (製作など) |
| 5月 | ・母の日のプレゼントを作る ・こいのぼりの絵を描く ・かぶとを作る |
11月 | ・秋の歌を歌う ・どんぐりや落ち葉で遊ぶ ・ごっこ遊びをする |
| 6月 | ・父の日のプレゼントを作る ・雨の歌を歌う |
12月 | ・クリスマスリース作り ・クリスマスの歌を歌ったり、聞いたりする |
| 7月 | ・七夕の飾りを作る ・シャボン玉遊びをする |
1月 | ・お正月遊びをする(かるた、すごろく、ふくわらいなど) |
| 8月 | ・花火やひまわりの絵を描く | 2月 | ・鬼のお面を作る ・豆まきをする ・画用紙で雪だるまを作る |
| 9月 | ・敬老の日のプレゼントを作る ・お絵かきをする |
3月 | ・折り紙で雛人形を作る ・粘土遊びをする |
全国のさまざまな病児保育室の保育士さんや看護師さんのお話を聞いてとても勉強になりました。
その中でも今回は次の二つのことを取り上げてみました。
・病児保育室の必要性について
母親の立場から 子どもが病気になった時
自分か主人が仕事を休む(職場の責任で休めない)、近所の人に見てもらう(なかなか頼めない)
↓病児保育があるということは
精神的な不安が少なくなり、ゆったりと仕事と育児が両立できるようになったそうです。
私たちも保護者の方が安心してお子さんを預けられ、ゆったりと仕事ができる病児保育室にしていきたいと思っています。
・子ども一人一人の情報を知るために
個人ファイルを作り保管(アレルギーをもっている、けいれんを起こしたことがあるなど見落としのないように)
ファイルの色 赤(けいれん)、黄(アレルギー)、クリア(風邪)などでわけているそうです。
さくらではアレルギーあり、なしの情報を見落とさないように個人ファイルがあり、管理されています。
また利用されるたびに確認のため保護者の方にアレルギーと食事制限のあり、なしを聞くなどして間違いのないようにしています。
研究会に参加して他にもいろいろな病児保育室の様子を聞いて、これからも子どもたちが安心して楽しく過ごせて健康を回復できるよう努めていきます。
|
|
| 午前9:00 → | 10:00 → | 11:30 → | 1:00 → | 3:30 → | 5:00 |
| 診察 | 検温・おやつ 自由遊び |
昼食 | 検温 お昼寝 |
検温・おやつ 自由あそび |
お迎え 診察 |
病児保育室直通電話 080-5237-9833
メールアドレス 28sakura5570@ezweb.ne.jp
ただし、お昼寝の時間(13時~15時まで)は避けてください。予約も受け付けていません。
去年登録されている方も、今年また新たに登録していただく必要があります。登録は小児科外来か津山市社会福祉協議会事務所で受け付けています。
これからも職員一同がんばっていきたいと思いますので登録をよろしくお願いします。
昨年は第15回全国病児協議研究会が岡山で開催され、その数日前、山陽新聞で県内の病児保育室の紹介とその役割が取り上げられました。病児保育には保育と看護の両方の専門性が必要となります。協議研究会の目的は保育士は看護の知識を、看護師は保育に対する理解を深め、‘保育看護’の質を向上させることにあります。岡山大会では7月17・18日の2日間で全国から850名の参加がありました。 |
|||||||||||||||||
◎病(後)児保育の歴史 昭和41年6月、東京・世田谷の民間保育所であるナオミ保育園の保護者によって、園内方式の「病児保育室バンビ」が誕生する。その2年後の昭和44年4月、大阪・枚方市民病院内に地域センター方式の「枚方保育室」が設立された。ともに働く母親を中心とする市民運動から秒時保育室の誕生となった。それ以後、平成3年までに全国12箇所に誕生し、同年3年9月全国病児病児協議会が設立された。 http://www.byoujihoiku.ne.jp ◎タイプ別保育数
岡山大会プログラム
ステップアップ研修「繰り返す発熱、鼻水をどう考えるか」では保育の現場で子どもたちの度重なる発熱や鼻水にどう対応していいのか悩んでいたという保育士さんの熱心な質問がありました。 また分科会の③家族・地域関係ではこぐま福祉会こぐま子どもの家(福岡県)の社会性と言語面に遅れのある兄弟児のケア、八尾徳州会小児科の自閉症やADHDなどの軽度発達障害児が病児保育室を利用したときの対応、中部学園短期大学すずらん病児保育園の子育て中の保護者を対象にしたすずらん保健室を開設し、これからの病児保育室は子どもを預かるだけでなく地域の子育て支援の場としての重要であるという発表、光久福祉会池尻保育園(大阪府)は狭山市の子育て支援の理念「一人一人の個性を大切にして豊かな心を育てましょう」の紹介などがありました。今大会のテーマは『地域で子どもたちが健康で輝いた生活を送るための環境づくり』でした。今、子どもたちを取り巻く社会は、健康上の問題ばかりでなく、虐待、地域社会の希薄化、育児放棄など社会問題が深刻化しています。そんな社会で病児保育室の役割も多様化してきたことを感じさせられました。今年は、大阪大会です! |
|||||||||||||||||