病児保育室だより 第3号 松尾小児科内 病児保育室さくら |
二学期は保育園、小学校では運動会、お月見、遠足など楽しい行事もたくさん・・・・。一年中で最も充実した時期ですが、体調を崩しやすいのもこの季節。お子様の健康管理には十分注意したいものです。‘さくら‘では年令や病状にあわせ、家庭的な温かい雰囲気を大切にして、子供の思いや要求を受けとめた遊びや季節の行事を取り入れています。折り紙や製作、歌・・・楽しい思い出をもっ て帰ってもらえるように工夫しています。
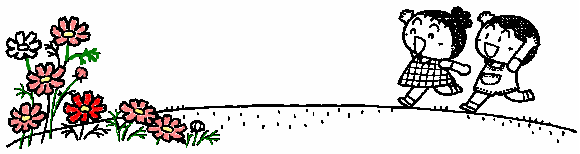
<おねがい> 予約をしていても 当日キャンセルの方はお手数ですが、 必ずご連絡ください。 |
“さくら”での子どもたちの様子
|
こま、やじろべい、指人形、モビール、みんな、あるものからつくりました。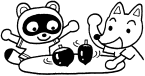 あるものとは あるものとは何でしょう? それはどんぐりです。 |
「落ち葉や木の実でままごとだってできるよ。」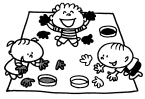 “さくら”にあるおままごとセットに木の葉や木の実を使ったごちそう。 |
|
 敬老の日は9月20日 「おじいいちゃん、おばあちゃんお元気ですか?こんどかたをたたいてあげるからね。」 長い年月を生きてきた人たちに尊敬と感謝を表す日です。昨年“さくら”にきたYちゃん。 おばあちゃんにペンダントを作りプレゼントしたね。 |
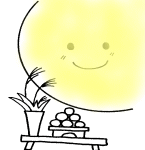 中秋の名月は9月28日です。 「お月様はどうして○○チャンのあとをついてくるの。」 と聞かれたお母さん。 「○○チャンがすきだからよ。」 お母さんも子どもの時、こんな経験をしたことを思い出しました。 |
|
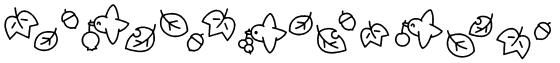
| 9月 虫の声 お月見 敬老の日 |
・虫の声を聞いたり折り紙をする。(裏庭や川土手から聞こえてくるよ。) ・お月見の話をしたり、歌を歌ったり、絵本を読んだりする。 ・敬老の日のプレゼントを作る。 |
| 10月 収穫の秋 (秋の自然物) |
・どんぐり、まつぼっくりで遊ぶ。(ままごと、製作など・・・) ・野菜のスタンプ遊びをする。(さつまいも、ピーマン、にんじん・・・) ・野菜の水栽培を楽しむ。 |
| 11月 文化の日 勤労感謝の日 七五三 |
・落ち葉やどんぐりで遊ぶ。 ・ゲーム遊びやごっこ遊びをする。(言葉のやりとりを楽しむ。) ・千歳あめ袋を作る。 |
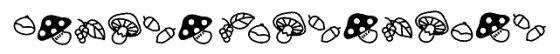
さる7/18・19日に横浜市区民文化センターで第14j回全国病児保育研究会が開催されました。“病児保育協議会”という団体をご存知ですか?始めて耳にされた方も多いのではないでしょうか。この協議会は病気のかかっている子どもの健康と幸福のために、専門家集団(保育士、看護師、意思、栄養士等)によって看護と保育を行い、子供たちの健康と幸福を守るという思いから平成3年に発足したものです。発足当時は全国で14施設でしたが、現在では全国約280施設が加盟しています。
(詳しくお知りになりたい方はホームページをご覧ください。http//www.byoujihoiku.ne.jp)
さて、今回の大会には2日間で約700人の参加があったそうです。病児保育室を開設しているのは医院や病院ばかりではありません。保育所型、乳児院型、単独型とあり、今回の参加者も医師、看護師、保育士、栄養士、そして、病児保育室を運営している保護者会の代表の方と職種はいろいろです。この大会の目的は、病児を対象としている点で保育士は保育の専門知識に加え乳幼児の発育、病気に知識を深め、看護師は看護の専門性は、帆足英一先生の“病児・病後児保育の課題と問題点”、横浜市立大学教授の横田俊平先生の“子どもと感染症”という2つの講演がありました。帆足先生は“小児有病児ケアに関する研究班”の一人として協議会設立に関わった方です。横田先生の講演は一般的に私たちがよく耳にする麻疹、水痘病、りんご病といった感染症についてスライドを交えながら、わかりやすく説明してくださいました。
2日目は分科会。いろいろなテーマにわかれ発表がありました。私が参加した「病児保育のニーズと問題点」についてお知らせします。
当病児保育室の方針“病気のときはできるだけ保護者がそばにいてあげて欲しい”、“こどもといる時間を大切にして欲しい”ということより基本的には延長保育を行っていない。しかし実際には 0~30分・・・36% 30~1時間・・・6% 1時間~・・・2%で延長保育を行っている。
(対策)
・当院の方針をのせたお便りを配り、保護者の理解を呼びかけたり、無理なときはファミリーサポートを紹介する。
・お迎えの時間の前に退社できるように職場での病児保育に対する理解を深める。(広報活動を行う。)
(参加者の声)
・6時までを通常保育にしてもらえば、大半の保護者がお迎えの時間に間に合う。(病児保育室の保護者代表のお母さん)
・まったく延長保育を行わないのではなく、多少の延長保育を行うことが母親の育児の負担を軽くし、幼児虐待などが行われる今の社会では子供の支援につながる。 (小児科医 帆足先生)
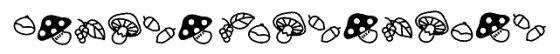
枚方病児保育室は枚方市の香里団地にあり、今年で35年目を迎える自治体主体としては全国で初めてつくられた病児保育室です。開設には団地内の若い父母の熱心な要請があったそうです。この発表も、保護者のお父さんでした。現在この団地は住民の老齢化、世帯数の減少で利用者が減少の傾向にあるとのこと。今回は利用者、非利用者1000世帯に対して、保育内容の向上と利用者増に結びつけることを目的にアンケートをおこなったそうです。今もこうした熱心な取り組みが行われているのですね。
3.ベアーズデイサービスセンターの7年の検討
谷本こどもクリニック、保育園ベア-ズに隣接する定員6名の病院併設型施設。米子市ばかりでなく、周辺の市町村からの利用も可能で、昨年の利用者は1000人以上。クリニック、保育園から常時スタッフをまわすため、子どもの病状、年令を考慮し6室ある全保育室を使って対応しているとのこと。理想的ではあるが、参加者からはあまりに細かく保育室を分けすぎているため閉鎖的になり、子供同士の関わりをもっと大切にすべきではとの声も上りました。また利用者状況を検討した結果では、1歳児が全体の1/3を占め、そして、集団保育一年目の子供が多いとのこと。集団保育二年目以降にはぐっと利用が減るそうです。いかに子供が新しい環境に慣れるのがたいへんなのかがわかりますね。
横浜市にある保育所併設型の病児保育室です。通常保育と病児保育の両方を行う立場から、現在かかえている病児保育の問題点について発表が行われました。
(問題点)
・従来、病気明けの子供を通常保育の中で受け入れていたため、保護者の目からみて同程度の場合には有料の病児保育室を利用したがらない。
・保護者の病後児に対しての認識差がある。
・通常保育と病後児保育の区別を明確にするのは困難。
(対策)
・保護者に対して病気や予防に対する意識の向上を促す。(お便り、保護者会等)
・集団保育での病気の対処と他の子供への配慮を保護者に深める。(保険知識の必要性)
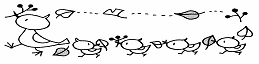
* ある看護婦さんからの質問*
「あるお母さんさんから‘同じ日に三つの違う病院でそれぞれ違うワクチンを接種してもいいですか?‘と尋ねられたのですが・・・。」
* 横浜市立大学の横田先生の返答*
「アメリカにいた時に私の娘は、麻疹、風疹、ポリオ・・・
と七種類のワクチンを一日にしました。」
決してこんな方法をお勧めしているわけではありません。
| 当日はこの他にも‘遊びと環境‘、‘食事の工夫‘、‘ヒヤリハット事例とその対策‘など多数の分科会が行われました。参加者の大半が当施設のような小規模のものです。それにもかかわらず、熱心な参加者の様子にこれからの時代の病児保育の必要性を感じずにはいられませんでした。又、分科会の最後に帆足先生から‘地域にあった病児保育室を‘と言うお話がありました。そうですね。病児保育室をとりまく環境はそれぞれ異なります。私達にできる、地域にあった病児保育室にしたいものです。 |
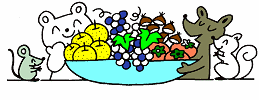
 先生と一緒に遊ぼう
先生と一緒に遊ぼう